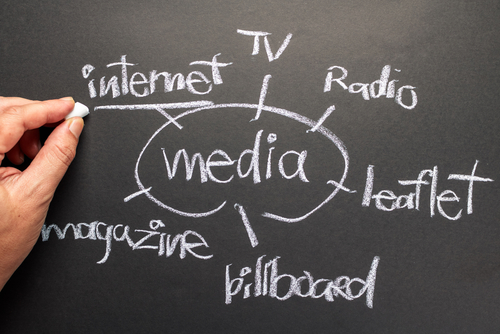日々のマーケティング活動において、使える時間とコストは限りあるものですが、それらを有効に使いたいと考えるのは当然でしょう。
際限なくリソースをつぎ込み、新規顧客を獲得し続けることができれば楽ですが、現実的ではありません。
そこで役に立つのがリテンションです。
今回はそんなリテンションについて解説していきます。

リテンションってどういう意味?
まずリテンションとは、保持、保留、維持を意味する英語から来ており、マーケティング用語としては「既存顧客の引き止め」を意味しています。
一度自社製品を購入してくれた顧客を引き止め、継続的に興味を持たせ続け、別の製品やサービスを購入してもらえるような施策や活動が、リテンションマーケティングです。
マーケティングの世界では「1:5の法則」と呼ばれるように、新規顧客を獲得するのには既存顧客を維持するよりも5倍のコストがかかりますが、それよりも既存顧客と良好な関係を築き維持する方が費用対効果に優れています。
また、人事界隈の用語にもリテンションがありますが、そちらは自社の有力な人材が外部に流出しないような施策を意味しますので、注意が必要です。
リテンションのメリット

上記の通り、新規顧客の獲得よりも費用対効果に優れている点が最も大きなメリットとなっています。
新規顧客は獲得にコストがかかる上に、購買金額が低く利益率が低いのが特徴です。
自社の安定的な成長のためにはより、利益率の高い既存顧客をいかに引き止め継続的に購買してもらうかが重要なのです。
また、CRM(Customer Relationship Management)もリテンションマーケティングの一環であり、顧客関係の管理をすることで既存顧客だけでなく今後良い関係を築けそうな見込み顧客の発見に繋げることができます。
つまり既存顧客との繋がりから新規顧客の獲得さえも可能になることを意味しています。
その他にも顧客からのフィードバックを得ることで品質向上とともに市場のニーズをより正確に収集することができます。
それを活かして次なる見込み顧客や新規顧客の引き込み、離反顧客の引き戻しなども見えてきます。
リテンションの具体的な方法
良いことづくめなリテンションですが、継続的な興味や購買意識を持ってもらうには、魅力的な企業であることが必要です。
接客時の態度やサポート対応で特別感や悩みの解決に繋げること、充実したアフターフォローによる安心感、ポイント制度などでお買い得になったり、いずれにせよもう一度利用したいと思わせられるかどうかがポイントになります。
また、定期的な接触も重要なポイントですが、対面によるものだけでなくメルマガなどの情報発信で行うことが可能です。
単純接触効果に見られるように、繰り返し接触することで好印象を抱かせることができますので、定期的な情報発信で刷り込みを行うと効果的でしょう。
ただし、不必要な情報が多いと拒絶されやすくなりますので、顧客の求めている情報を常に検討しながら発信することが求められます。
また、違約金の設定などで顧客の囲い込みを行う企業も見受けられますが、不信感を抱かせ顧客の流出に繋がりかねないので避けた方が無難です。
リテンションで重要なポイント

リテンションで最も重要なのは、顧客データの管理と運用です。
CRMについて少し触れましたが、顧客情報をデータベース化し管理することで購入履歴やサイトへの訪問履歴、DMの開封率といった情報を得ることができます。
むしろこれらの情報無くしてリテンションマーケティングを行うことは不可能と言えます。
データベースはエクセルなどの表計算ソフトで代用することも可能ですが、規模が大きくなると限界が生じてきます。
データベースソフトの導入がリテンションの目的ではありませんが、定性的なデータがあって初めて行える施策ではありますので自社に合ったスタイルを選ぶようにしてください。
また、データベースを用いて顧客管理をすることで、購買金額や頻度の大きい優良顧客(ロイヤル顧客とも呼ばれます)が見えてきます。
それらの優良顧客に特別な割引や限定商品、カタログといった限定的な優遇を行うことも効果的です。
まとめ
リテンションとは、「既存顧客の保持」を意味しており、新規顧客の獲得よりも費用対効果に優れています。
また既存顧客の保持を行う中で、見込み顧客の発見や新規顧客との繋がりが得られることもあり、企業としては行わない手はない施策でしょう。
ただし、そのためには顧客データの管理運用が不可欠であり、定性的なデータ無くしてリテンションマーケティングを行うことはできません。
データベースの活用は確かに導入コストもかかりますし、運用コストも無視できませんが、限りあるリソースをどこに使うのか、利益率を上げていくのかを検討する武器となるでしょう。
企業やブランドの性格にもよりますが、新規顧客の獲得に注力するだけでなく、すでに関係性のある既存顧客にも目を向けてみると新しい発見があるかもしれません。